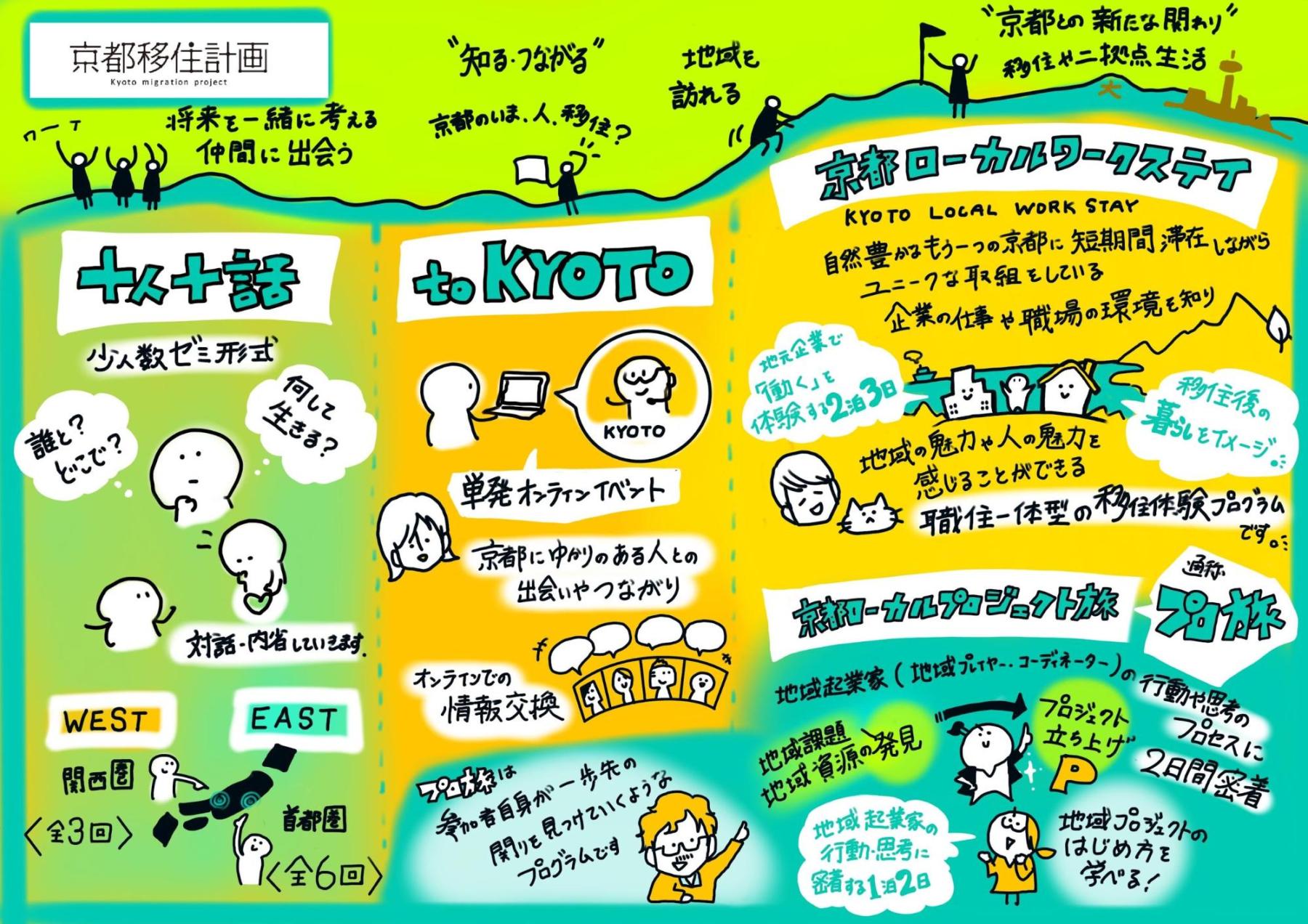「二拠点生活や移住に興味はあるけれど、移住先ではどんな仕事や暮らし方ができるんだろう?」と疑問を持ったことはありませんか?
「京都ローカルワークステイ」は、京都府のローカルエリアでユニークな取り組みをしている企業やプロジェクトの魅力を知り、副業・兼業・プロボノなど、地域との多様な関わり方を見つけ、深めていく伴走型のプログラムです。
今回は、「京都ローカルワークステイ」の運営メンバーと、2024年度のプログラム受入企業である「道の駅 海の京都 宮津(ハマカゼプロジェクト株式会社)」の担当者・参加者の皆さんに、今年度のプログラムの振り返りや、今後目指したいチャレンジについて、お話を伺いました。
3年目を迎えた、「京都ローカルワークステイ」とは?
まずは、ローカルワークステイの運営メンバーである株式会社ツナグムの藤本和志(ふじもと・かずし)、株式会社ローカルフラッグの高橋友樹(たかはし・ともき)さんに、「ローカルワークステイ」の全体像をお聞きしました。

藤本
ローカルワークステイは、地域の特性を活かしながら事業活動を行う面白い企業さんと、京都に関わりを作りたい人たちとの接点をつくる取り組みとして、京都府の移住促進事業の一環として行っています。今年度で3年目を迎えました。京都の「まちなか」というよりは「ローカルエリア」、特に北部を中心に展開しています。
京都のローカルエリアが抱える課題や、移住に興味のある人の関わり方の難しさにはどんな問題があるのでしょうか。
藤本
移住者が暮らしのイメージを描くなかで、「仕事」がボトルネックになることが多くあります。「一体、どんな仕事や働き方があるのか?」ということがイメージできないんですね。都会であれば大手求人サイトから職探しができますが、ローカルでは身近で採用することが多いことも理由のひとつ。ローカルワークステイでは、この問題解決の糸口として、移住希望者と企業の接点や、「関わりから見つける働き方づくり」を目指しています。
2024年度は、今回お話しをお聞きする宮津市の「海の京都 道の駅 宮津(ハマカゼプロジェクト)」のほか、与謝野町や舞鶴市や京丹波町など4社が受入企業に。
参加者は、希望する企業の開催日程にあわせ、企業や地域についてオンラインで学ぶ「事前学習」、実際に地域企業の課題解決に取り組む3日間の「現地体験」を経て、企業や地域と持続的な活動につなげていく「プロジェクトづくり」を実践しました。

各社の事業内容や課題はさまざま。ローカルワークステイの運営事務局では、「課題は分かるが、自分に何ができるかわからない」という状況から、「都市部からローカルに足を運んでもらう」ことを大切にしながら、有機的な関係づくりにつながるサポートをしているのだそうです。
与謝野町を拠点に、地域づくりを支援する株式会社ローカルフラッグの高橋さんは、現地に密着したコーディネーターを担当しました。

高橋
プログラム1、2年目は、自身のスキルや経験を活かしながら関わり方をうまくキャッチアップできる人もいれば、それを難しく感じている人も見受けられました。そこで、今年は特に事前学習会で参加者同士の交流やインプットの時間を多く取りつつ、全員の目線合わせをおこないました。
新たな取り組みを経て、今年度はどのような変化があったのでしょうか?
高橋
例年、企業ごとの「テーマ」に対してアウトプットを考えてもらうのですが、すべてのプロジェクトで関わり方の熱量がさらに向上しましたね。一人ひとりが「関わりしろ」を見つけて、企業の課題に対してプラスアルファの提案もできているのが印象的でした。企業の皆さんも、参加者の皆さんが出したアイデアに対して積極的に受け入れ、動いてくれていて、いい循環が生まれています。
「道の駅」の可能性を広げるため、ワークステイの受け入れ企業に
そんな“いい循環”が生まれている一つが、今年度の受入企業である「道の駅 海の京都 宮津(株式会社ハマカゼプロジェクト)」です。駅長の浜崎希実(はまさき・のぞみ)さんにお話を伺っていきます。

「道の駅 海の京都 宮津(以下、道の駅)」は、宮津市中心部・浜町地区にあり、日本三景・天橋立に一番近い道の駅。地元の農家さんが、毎日旬の野菜を届けてくれる「宮津まごころ市」と、宮津・丹後の新鮮な魚介類を楽しめる「おさかなキッチンみやづ」と観光案内所が併設されています。
浜崎
道の駅には、たくさん観光客が来られますが、多くの方の目的地は天橋立です。「もっと宮津や丹後のファンになってもらえる方法はないだろうか?」「道の駅の商品を通じて、食材のこだわりや、生産者を知ってもらう機会を作っていけたら」 と考えているときに、京都ローカルワークステイの取り組みに声をかけていただき、参加者の皆さんと一緒にこの課題に取り組みたいと思いました。

また、地元の農作物を販売する道の駅ならではの視点で、まちの課題と感じていることもありました。
浜崎
農家さんは人手がいる時といらない時があり、繁忙期の人手不足が課題になっています。そのことを道の駅から発信し、繁忙期の手助けができる人と農家さんをつなぐ仕組みはできないだろうか、ということも日ごろ考えています。一般的な「道の駅」の業務ではないかもしれませんが、「農家さんの課題をまとめて解決できる道の駅」になりたいと思っているんです。
宮津に足を運んで、話を聞いて得られたこと
続いては、道の駅プロジェクトへの参加者から、星野正太(ほしの・しょうた)さん、佐藤 花奈(さとう・かな)さんに詳しくお話を伺ってきます。
京都ローカルワークステイを知ったきっかけや、参加しようと思ったきっかけはどんなことだったのでしょうか?

星野
私は、過去の参加者である知人がSNSで「京都ローカルワークステイ」の募集について発信をしていたことがきっかけです。生まれも育ちも東京ですが、仕事の関係で東北に住んでいたことがあります。地域での暮らしや魅力を知ったことで、場所を問わず「ローカル」を盛り上げたいという気持ちを持っていました。そんなときに「京都ローカルワークステイ」のプログラムを見つけて。京都には中学校のときの修学旅行や旅行で数回来たことがあっただけで、縁もゆかりもほぼないに等しい場所でした。

佐藤
私はいま京都市内に住んでいますが、もともと道の駅がすごく好きで……! 去年は1年間秋田県にいたのですが、そのときに道の駅巡りにハマり、100箇所近くの道の駅を巡りました。京都移住計画の案内で「京都ローカルワークステイ」を知り、「道の駅に関するプロジェクトに携わりたい!」という想いから参加を決めました。
参加してみてどんなことを考えたり感じたりしたのでしょうか。



星野
あたりまえかもしれませんが、自分で足を運ぶことで得られること、感じられることは圧倒的に多いですね。気候も、どんな人が住んでいるのかということも行ってみないとわからないですし、現地を訪れたからこその良さに気づけました。
たとえば観光で来ただけでは、地元の農家さんや漁師さんなど、生産者の方々と関わり、腹を割ったお話を伺うことはなかなかできません。実はプログラムが終わってから、出会った生産者からお魚やレモンを購入させていただいたりもしていて。これまで縁もゆかりもなかった場所に新たな繋がりができたような気がして、とても嬉しく思っています。
佐藤
私は関東出身で、今まで京都に「宮津」という地域があることも、天橋立が宮津にあることも知らなかったので、そのことも学びでした。「道の駅巡り」をしていた観点からは、観光地ってその県の特有のお土産が多くを占めている印象なのですが、宮津もしくは近隣で採れた農作物しか置いていないということが、面白いなと思いました。スーパーとはまた違い、生産者の名前を知って、その人を想いながら買うことができることが素敵だと思います。
「コピーライティング」のスキルと「道の駅巡り」の趣味を活かして
現地での体験の後は、テーマに沿ってそれぞれのプロジェクトを推進しています。道の駅プログラムから生まれた2つのプロジェクト、「道の駅のコピーを作る」「道の駅のスタンプラリー」についてお聞きしてみましょう。
本業でコピーライターとして働く星野さんは、そのスキルを活かし「道の駅のコピー」を主導しています。
星野
道の駅のホームページには「市街地まるごと道の駅」というキャッチコピーがついていますが、こちらとあわせて、より“道の駅 宮津らしさ”が伝わり訪れてみたいと思ってくれる方が増えたり、浜崎さんはじめ道の駅として取り組まれるこれからの挑戦を応援できたりするような言葉を作っていけたらと思っています。

浜崎さんの協力のもと、地域の皆さんにインタビューをしながらまとめているそうです。
道の駅が大好きな佐藤さんは、各地の道の駅を巡ってきた経験も活かしながら、自身と同世代の大学生へ向けた施策を「地域をまわるスタンプラリー」として検討しています。
佐藤
現地でお話を聞いたとき、「魚には“旬の旬の旬”がある」という地元の人の言葉が印象的でした。その時期に一番おいしいものを食べるという楽しみが叶えられたらというのと、宮津は冬の客足が落ち込むと聞いたので、1年を通して道の駅に来てもらえるよう、春夏秋冬それぞれに訪れたくなるようなスタンプラリーを考えています。

プログラム終了後も楽しみな企画が生まれそうな道の駅。外の視点を活かし、自社に関わってくれる人がいることを、浜崎さんはどのように受け取っているのでしょうか。
浜崎
皆さん積極的で、「こんなことがしたいです!」と提案してくれるのが何よりも嬉しいです。道の駅をいっぱい見てきた佐藤さんに、普段当たり前に取り組んでいた、道の駅のこだわりを褒めてもらえて、それが特別な事だったと知れたこともそうですし、星野さんのコピーライティングのためのインタビューでも地域の皆さんからいい話が続々と出てきて、さらに熟考してもらっていて。お二人自身にファンになってもらっているのが伝わりますし、それだけでも価値があったと感じます。
京都ローカルワークステイの「これまで」を振り返りながら
プロジェクトの完成も間近。参加者のお二人に、今後チャレンジしたいことについてもお伺いしました。
星野
コピーに携わる中で、ほかにも発信に役に立てる余地があると感じました。現地で取材をさせてもらったり、タブロイド紙を作ったりとやり方はさまざまにありそうなので、スモールステップで取り組みつつ、浜崎さんをはじめ地元の皆さんと意見交換をしていきながら、力になれることを探っていきたいです。
佐藤
私自身は大学の都合で2月末で京都を離れてしまいますが、何度も訪れたくなるような「道の駅のスタンプラリー」を実現させて、また宮津に行けるように頑張ります。それから、今後も色んな地域を楽しみながら、日本のすべての道の駅を巡ることも夢です!

運営メンバーはこの3年間を振り返り、どのような心境でしょうか?
藤本
3年の間に、この取り組みがしっかり根付いてきたなと感じます。星野さんも知人づてでこの取り組みを知ってくれたとのことですが、参加者にも企業にも、行政にも徐々に浸透してきたと実感しますね。
高橋
受入企業も3年のあいだに10社ほど増えました。特に、自社から外向けに発信してくれる企業さんが増えたと思います。企業が広報活動を行うというマインドに変わっていくことで、まちの魅力も広がり、結果的に移住にも繋がると思っているので、嬉しい変化ですね。

実際に、京都北部には来たことがなかったという方が与謝野町に移住をしたり、行政で働いていた人がローカルシフトで新しいキャリアを始めたり、という例があるのだそう。
藤本
移住や就職につながるのも嬉しいことですが、まずは「ゆるやかなつながり」が大切だと思っています。移住や就職を「する」「しない」の0か100ではなくて、その手前にお試しで働くイメージを持ってみる選択肢が、このプログラムを通じて、参加者・企業の双方に少しずつ広がってきたのかなと。
これを受けて、浜崎さんもこう言います。

浜崎
「生活のためにお金を稼ぐ仕事」は都会のほうが見つけやすいと思いますが、ローカルエリアでは、お金が最優先ではなく「この仕事が好きでやってます」というスタンスで、楽しんで働いている方も多いです。条件を絞ってネットで見つけることとは、見つけ方自体がちがうんですよね。ローカルワークステイを通して、「こんな仕事や生き方があるんだ」ということを、実感として持ってもらえるといいですね。
藤本
そうですね。ローカルではスキルやキャリア以上に、「想いやマインド」が大事にされる傾向があると感じます。例えば最初は1社でぴったりの働き方を見つけるのが難しくても、地域の方から「他の仕事も紹介してあげるよ」という声掛けがあったり、副業やアルバイトを複数行い、自分らしい働き方を見つけている移住者も多いです。ローカルワークステイは、「そういう仕事の仕方もあるんだ」と働き方の価値観が切り替わる機会になるかもしれません。自分らしい生き方や働き方に出合える場になれば嬉しいです。

経験やスキル・興味や関心事を活かして、京都ローカルの力になりたい思いをもった参加者の皆さんと、ローカルに密着しながらまち全体盛り上げる道の駅、そしてその二者のあいだに、さまざまなグラデーションの「関わりしろ」をコーディネートする京都ローカルワークステイ運営メンバーの皆さん。それぞれの想いや、プログラム参加後の変化をお聞きすることができました。
京都移住計画では、今後も様々なイベントやプログラムを実施していきます。ローカルに関わる生き方・働き方に興味をお持ちの皆さん、ぜひ一歩踏み出してみませんか?




執筆:弓削 智恵美
撮影:小黒 恵太朗
編集:北川 由依